台湾の電子署名法改正:デジタル契約の法的効力と実務対応
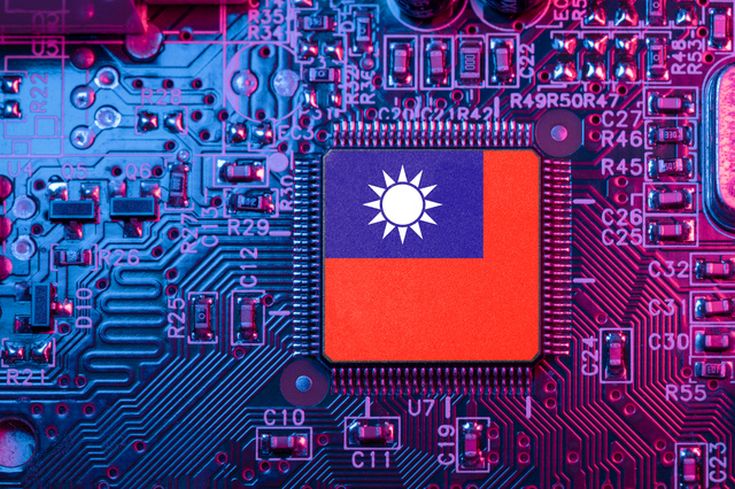
2024年、台湾のデジタル法制は歴史的な転換点を迎えました。2002年の制定以来、22年ぶりに抜本的な改正が行われた電子署名法(電子簽章法)は、台湾政府が推進するスマートネイション戦略の中核を成す法的インフラです。改正の目的は、デジタル経済の加速、行政手続きの完全オンライン化、国際的なデジタル貿易の拡大にあります。日本企業を含む外資系企業にとっても、台湾市場における契約実務やコンプライアンス体制の見直しを迫る重要な法改正といえるでしょう。
本記事では、2024年改正電子署名法の全容を詳細に解説します。特に、実務上のインパクトが大きい「推定効力」の導入、電子署名とデジタル署名の厳格な法的区分、日本法との比較分析に重点を置きます。急速に進化する台湾のリーガルテック環境において、日本企業が直面するリスクと機会を明らかにし、適切な対応策を提示します。
目次
台湾デジタル法制の変遷と2024年改正の背景
台湾における電子取引の法的基盤は、2002年に施行された電子署名法にその起源を持ちます。国連国際商取引法委員会(UNCITRAL)のモデル法を参照して設計され、電子ファイルや電子署名に対して物理的な文書や署名と同等の法的効力を付与することを目的としていました。しかし制定から20年以上が経過し、スマートフォンの普及やクラウドサービスの台頭、パンデミックによる非対面取引の常態化など、インターネット環境は激変しました。旧来の法体系では対応しきれない課題が浮き彫りになっていたのです。
特に問題視されていたのは、行政手続きにおける電子署名の利用が進まなかった点です。旧法では行政機関が独自の判断で電子署名法の適用を除外できる規定が存在しました。そのため多くの手続きで依然として紙と印鑑が要求され続けていました。また国際的なプラットフォームが普及する中で、それらの法的効力が台湾法上どこまで認められるのかという解釈の曖昧さも、企業のデジタルトランスフォーメーションを阻害する要因となっていました。
こうした状況を打破すべく、2022年に発足したデジタル発展部(MODA)が主導し、今回の法改正が実現しました。改正には明確な政策目標が込められています。第一に、電子形式であることを理由とした法的効力の否定を防ぐ「機能的等価性」の徹底です。第二に、特定の要件を満たすデジタル署名への強力な証拠力の付与です。第三に、技術的な連携を通じた国際的な相互運用性の確保です。
台湾における2024年改正の全容と法的構造分析

2024年の改正は、全17条から成る旧法を大幅に見直し、新たな概念定義や効力規定を追加する大規模なものでした。日本のビジネスパーソンが特に理解しておくべき主要な改正ポイントを分析します。
電子署名とデジタル署名の定義の明確化
日本企業が台湾法を理解する上で最大のハードルとなるのが、電子署名(Electronic Signature)とデジタル署名(Digital Signature)という用語の使い分けです。日本の電子署名法ではこれらは一つの概念の中で扱われることが多いですが、台湾の改正法では定義段階から明確に分離されています。
電子署名とは、電子ファイルに添付または関連付けられたデータであり、署名者の身分や資格を識別し、電子ファイルの真偽を確認するために用いられるものを指します。広義の概念であり、メールの署名欄、タブレットへの手書きサイン、一般的なクラウドサイン(立会人型)のログ、生体認証などが含まれます。
一方、デジタル署名とは、電子署名の一種であり、数学的アルゴリズム(公開鍵暗号方式)を使用し、署名者の秘密鍵で暗号化され、公開鍵で検証可能なものを指します。さらに政府許可の認証機関(CA)が発行した証明書に基づく必要があります。マイナンバーカード署名、商業登記電子証明書を用いた署名、認定事業者が発行する当事者型署名などが該当します。
この区分は極めて重要です。後述する推定効力は、デジタル署名にのみ付与されるからです。日本の立会人型(事業者署名型)の電子契約サービスは、台湾法上では広義の電子署名には該当します。しかし狭義のデジタル署名の要件を満たさない可能性があるため、リスク管理上の注意が必要です。
機能的等価性の徹底と同意プロセスの合理化
改正法は、電子ファイルおよび電子署名が、物理的な文書および署名と機能的に等価であることを宣言しています。電子形式であることを理由として、その法的効力を否定してはならないという規定により、書面性が要求される契約であっても、法律で特に除外されていない限り、電子データでの保存や署名が法的に有効となります。
また相手方の同意プロセスも合理化されました。旧法では電子形式の使用には相手方の同意が必須要件でしたが、改正法では同意の推定規定が導入されました。相手方に合理的な期間を与えて異議を申し立てる機会を提供し、その期間内に異議がなかった場合、相手方は同意したものとみなされます。
この規定により、見積書や発注書のやり取りにおいて、メールのフッターや取引約款に適切な文言を入れることで、個別の同意書を取り交わすことなくデジタル取引へ移行できる法的根拠が整備されました。ただし相手方はいつでも電子形式の使用を拒否し、紙の形式に戻すことを要求できる権利が保障されています。
行政機関による適用除外の制限
これまで台湾の行政DXを阻んでいた、各省庁が行政規則レベルで電子署名法の適用を除外できるという規定は削除されました。今後、行政機関が電子署名や電子申請を拒否するためには、法律による明示的な除外規定が必要となります。現在除外を行っている機関に対しても、施行から一定期間内に法整備を行うか、電子署名を受け入れる体制を整えることが義務付けられました。
台湾での会社設立、許認可申請、税務申告など、日本企業が現地で行うあらゆる行政手続きが、近い将来、完全にオンラインで完結するようになると考えられます。
台湾における推定効力の導入とデジタル契約のリスクマネジメント
本改正のハイライトであり、日本の法務担当者が最も注目すべき点が、推定効力の導入です。デジタル契約における紛争リスクの構造を根本から変えるものです。
推定効力のメカニズムと挙証責任の転換
民事訴訟において、ある文書が証拠として提出された際、その文書が本当に作成名義人(署名者)によって作成されたものであるか(真正な成立)が争点となることがあります。紙の契約書であれば、本人の印鑑があれば真正に成立したと推定されます。しかしデジタルデータにおいては、この推定が働きにくい状況がありました。訴訟において契約の有効性を主張する側(原告)が、複雑な技術的立証を行わなければならないという課題があったのです。
改正法は、政府の許可を受けた認証機関(CA)が発行した証明書を用いたデジタル署名について、本人によって署名されたものと推定すると規定しました。これにより挙証責任が転換されます。
日本企業が台湾企業との契約において、認定CA発行の証明書を用いたデジタル署名を使用していた場合を考えてみましょう。相手方が「署名していない」と主張しても、裁判所は一応「本人が署名した」ものとして扱います。相手方がその責任を免れるためには、相手方自身がなりすましなどの事実を立証しなければなりません。
日本企業における実務対応と使い分け
この法的効果の違いを踏まえ、契約の種類やリスクレベルに応じたプラットフォームの使い分けが推奨されます。低リスクの契約(NDA、発注書、社内承認など)では、一般の電子署名で対応できます。紛争になる可能性が低いため、簡便性を優先してよいでしょう。改正法により、電子形式であること自体で効力が否定されることはありません。
中〜高リスクの契約(基本取引契約、業務委託契約など)では、本人確認機能付き電子署名の利用が望ましいといえます。多要素認証(SMS認証等)を付加したグローバルプラットフォームを利用し、ログを残すことで訴訟時の立証を容易にします。
超高リスクの契約(M&A、金銭消費貸借、知財ライセンスなど)では、デジタル署名(政府認定CA連携)を使用すべきです。台湾の認証機関(TWCA等)の証明書を用いた署名、または認定CAと連携したプランを利用し、推定効力を確保して紛争時の法的地位を盤石にします。
台湾電子署名法における国際的相互運用性と日本との連携

台湾は国際政治上の制約から、他国と公式な外交条約(二国間協定)を結ぶことが難しい場合があります。法的な相互主義に基づく外国電子署名の承認において障壁となっていました。今回の改正では、外国の認証機関を承認する要件として、従来の国際互恵に加えて技術的相互運用性が新たに追加されました。
条約という政治的な枠組みがなくても、技術的なセキュリティ基準が同等であり、技術的な連携が可能であれば、MODAが外国の認証機関を承認できることになります。日本の認定認証事業者が台湾MODAの基準を満たし技術的相互運用性ありと認められれば、日本の電子証明書を使って台湾の契約書にデジタル署名を行い、台湾法上の推定効力を得ることが可能になるでしょう。
グローバルベンダーが採用する国際規格に基づく外国CAが広く承認されれば、普段使用しているプラットフォーム上で、特別な設定なしにデジタル署名としての効力を持つ署名が可能になる日も近いと予想されます。
台湾電子署名法と日本法との比較:経営者が知るべき相違点
日本の電子署名法と台湾の改正電子署名法は、共にUNCITRALモデル法の影響を受けているため、基本的な構造は似ています。しかし細部においては企業の法的リスクに直結する重要な差異が存在します。用語の定義について、日本では電子署名のみで、特定電子署名という区分はあるものの用語としては分かれていません。台湾では電子署名とデジタル署名を用語定義レベルで明確に区分しています。台湾の契約書でDigital Signatureとあれば、PKIベースの厳格な署名を指すため、用語の定義に注意が必要です。
推定効力の要件について、日本では本人だけが行いうる措置(秘密鍵の管理等)で行われたことが要件となります。台湾では政府許可CAが発行した証明書を用いたデジタル署名であることが要件です。台湾で推定効力を得るには、技術的な仕様だけでなく、どこのCAの証明書かが決定的に重要になります。
立会人型署名の扱いについて、日本では政府見解により、一定条件下で推定効力が及ぶと解釈される傾向にあります。台湾ではデジタル署名の定義に照らすと、純粋な立会人型は電子署名止まりとなる可能性が高いといえます。台湾での契約において、簡易なクラウドサインはデジタル署名としての強力な効力を持たない可能性がある点に留意が必要です。
台湾での電子契約導入に向けた実務対応ガイド
電子契約を導入する場合、まずは自社が台湾企業と締結している、あるいは締結予定の契約を洗い出し、リスクに応じたプラットフォーム選定を行う必要があります。契約書の条項についてもアップデートが求められます。台湾電子署名法に基づき、両当事者が合意した電子署名プラットフォームを用いて締結することを明記する電子署名の利用合意条項を追加することが考えられます。また電子ファイルが指定されたシステムに到達した時点で送達完了とみなす送達の特例条項も有用です。
推定効力が及ばない電子署名を利用する場合は、ログや監査証跡が証拠能力を有することを認め、形式面を理由に効力を争わない旨の証拠力の確認条項を入れることが重要なリスクヘッジとなります。本改正は技術と法律が交錯する高度な領域です。特に台湾の認証機関の利用手続きや、具体的な契約文言の調整には、現地法と日本法の双方に精通した専門家のサポートが不可欠です。
まとめ
2024年の電子署名法改正は、台湾がデジタル先進国としての地位を確立するための野心的な試みです。日本企業にとっても、より安全で効率的な取引環境が整備されたことを意味します。しかしその恩恵を享受するためには、電子署名とデジタル署名の違いを正しく理解し、適切なリスク管理を行うことが前提となります。
モノリス法律事務所は、IT・インターネット関連法務に特化した専門性を有し、台湾の法律事務所である椽智商務科技法律事務所と強固な連携体制を構築しています。椽智商務科技法律事務所は、日本の法文化やビジネス慣習を深く理解しています。この日台連携により、クロスボーダー契約の最適化、デジタル署名の導入支援、万が一の紛争解決に至るまで、法と技術の両面から日本企業の皆様を強力にサポートすることが可能です。台湾でのビジネス展開における法的課題については、ぜひ我々にご相談ください。
Contact お問い合わせ
日本語でのご相談が可能です。
台湾進出前のご相談から、進出後の法務対応まで幅広く対応しています。






