台湾進出の第一歩:現地法人・支店・駐在員事務所の違いと選び方
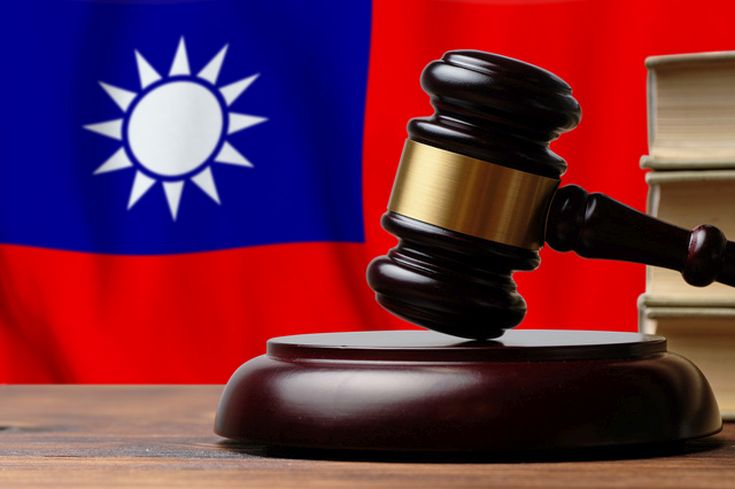
台湾は、日本企業にとって地理的な近接性だけでなく、高度なサプライチェーンの集積や親日的なビジネス環境、さらにはデジタルトランスフォーメーション(DX)の加速など、戦略的拠点としての価値を益々高めています。特に半導体産業を中心としたIT分野の隆盛は、多くの日本企業にとって台湾進出を検討する強力な誘因となっています。しかし、台湾でのビジネスを成功させるためには、その第一歩となる「進出形態」の選定において、法的・税務的な観点から緻密な検討が必要です。台湾の法体系は、日本の大陸法系を基礎としつつも、近年の会社法改正や外国人投資条例の運用、独自の税制である「統一発票」制度、さらには所得税法第25条に基づく特例措置など、日本法とは異なる独自の進化を遂げている部分が少なくありません。
進出形態には大きく分けて、独立した法人格を持つ「現地法人(子会社)」、日本本社の延長線上に位置づけられる「支店(分公司)」、そして営業活動を行わない補助的拠点である「駐在員事務所(代表人辦事處)」の3つの選択肢があります。これらは、台湾会社法(公司法)および外国人投資条例に基づき、認められる活動範囲や、日本本社が負うべき法的責任の範囲、さらには利益還流時の税率において大きな差異が生じます。特にIT関連企業においては、拠点の種類によって必要となる許認可や、NCC(国家通訊伝播委員会)等の当局への対応も異なります。
本稿では、最新の法令および判例に基づき、日本企業の経営者や法務担当者が台湾市場へ参入する際に直面する実務的な論点を網羅的に解説し、最適な進出形態を選択するための指針を提示します。
目次
台湾進出における主要な3つの形態と選択の基準
台湾への進出を検討する際、まず整理すべきは、現地で「営業活動(収益を伴う取引)」を行う必要があるか否かという点です。台湾の経済部(日本の経済産業省に相当)の統計によれば、日系企業の進出案件のうち、約80パーセントが現地法人、約10パーセントが支店、残りの約10パーセントが駐在員事務所という構成になっています。この傾向から、多くの日本企業が長期的な事業展開を見据えて独立した法人格を選択していることが伺えますが、事業のフェーズや目的によっては、他の形態が適している場合もあります。
営業活動、すなわち売上の計上や契約の締結を台湾国内で行う場合は、現地法人または支店のいずれかを選択しなければなりません。一方、市場調査、情報収集、日本本社との連絡業務、あるいは商品調達のための検品や連絡に限定される場合は、駐在員事務所の設立が検討対象となります。駐在員事務所は「営業行為」を行うことが禁じられており、この境界線を越えた活動を行うと、会社法に基づく罰則の対象となるリスクがあります。
以下の表は、各進出形態における主要な特徴を比較したものです。
| 項目 | 現地法人(子会社) | 支店(分公司) | 駐在員事務所(代表人辦事處) |
| 法人格 | 台湾法に基づく独立した法人 | 日本本社の延長(非独立法人) | 非独立法人・非営利組織 |
| 営業活動 | 可能(制限なし) | 可能(制限なし) | 不可(補助的活動のみ) |
| 本社の責任 | 出資額に限定(有限責任) | 日本本社が全責任を負う | 日本本社が全責任を負う |
| 税務申告 | 全世界所得に対し申告義務 | 台湾域内源泉所得に対し申告義務 | 原則として不要(費用のみ) |
| 利益還流税 | 配当に対し10%〜21%の源泉税 | 源泉税なし(送金自由) | 対象外 |
| 設立難易度 | 高い(FIA申請が必要) | 中程度(経済部への登録) | 低い(届出・登録) |
進出形態を決定するにあたっては、単なる手続きの簡便さだけでなく、将来的な事業拡大の可能性、税務コストのシミュレーション、そして日本本社に及ぶリーガルリスクの範囲を総合的に勘案することが、後のトラブルを未然に防ぐ鍵となります。
台湾現地法人の設立:有限公司と股份有限公司の選択とガバナンス

現地法人を設立する場合、台湾の「外国人投資条例」に基づき、経済部投資審査司(旧投審会)に対して投資許可(Foreign Investment Approval, 以下「FIA」)を申請する必要があります。現地法人は日本本社とは完全に別個の法的実体となるため、台湾国内で発生した債務や不法行為責任は、原則として現地法人の資産範囲内に限定されます。これは、特に製造物責任や大規模な労働紛争のリスクがあるビジネスにおいて、日本本社の資産を保護するための極めて重要な壁となります。
現地法人の形態としては、主に「有限公司(Limited Company)」と「股份有限公司(Company Limited by Shares)」の2種類が利用されています。これらは日本の「合同会社」と「株式会社」にそれぞれ類似した性質を持っていますが、台湾独自の規定も多いため注意が必要です。
有限公司(有限会社)の特徴とメリット
有限公司は、人的結合の性質が強く、少人数の出資者で機動的な運営を行うのに適した形態です。2018年の会社法改正以前より、1名の株主(法人または自然人)で設立可能であり、全額出資子会社を設立する日本企業の多くがこの形態を選択しています。
有限公司の大きな特徴は、ガバナンス構造のシンプルさにあります。最低1名の董事(取締役)を置けば足り、監察人(監査役)の設置は義務付けられていません。また、持分(日本の「持分」に相当)の譲渡には、他の出資者の過半数の同意が必要とされるなど、閉鎖的な組織運営が前提となっています。そのため、外部からの資金調達を予定せず、日本本社の100パーセントコントロール下に置く小規模から中規模の拠点に最適です。
股份有限公司(株式会社)の特徴と将来性
股份有限公司は、資本の結合を重視した組織形態であり、株式を発行して資金を募ることが可能です。将来的な現地でのIPO(新規公開)や、外部投資家からの出資受け入れ、従業員へのストックオプションの付与などを検討している場合は、この形態が必須となります。
ガバナンス面では、原則として最低3名の董事と1名の監察人が必要ですが、2018年の改正により、非公開会社(閉鎖性股份有限公司)であれば、董事1名、監察人1名といったスリムな構成も認められるようになりました。ただし、有限公司に比べると株主総会の招集や議事録の管理、株式名簿の備付など、会社法上のコンプライアンス維持コストは高くなる傾向にあります。
日本企業が単独で投資する場合、法人が1名の株主となることが可能であり、この場合は取締役会が株主総会の職権を代行できるなど、意思決定の効率化を図ることも可能です。
支店(分公司)の法的性質と日本本社への責任波及リスク
支店は、日本本社という一つの法人が、台湾国内で継続的に営業活動を行うための物理的な拠点に過ぎません。そのため、支店自体には独立した法人格はなく、支店が行った契約上の義務や不法行為に基づく賠償責任は、直接日本本社に帰属することになります。
この「日本本社と同一主体」であるという性質は、実務上、大きなリスクを孕んでいます。例えば、台湾支店で発生した未払債務や労働災害、あるいは知的財産権の侵害について、台湾の債権者は直接日本本社の資産を差し押さえる、あるいは訴訟を提起することが可能です。台湾の最高法院(最高裁判所)の考え方に基づけば、支店は本社の「延長」であり、法的な権利義務は不可分であるとされています。
一方で、支店形態を選択する最大の動機は「税務上の効率性」にあります。現地法人の場合、台湾で得た利益を日本本社に配当として送金する際、日台民間租税取決めを適用しても10パーセント(国内法では21パーセント)の源泉徴収税が課されます。しかし、支店の場合は「同一法人内の内部送金」とみなされるため、支店での利益送金時には源泉税が課されません。
また、支店での赤字を日本本社の所得と合算(損益通算)できる場合がある点も、立ち上げ初期の節税メリットとして挙げられます。これは台湾税法上の効果ではなく、日本側の法人税法に基づく取扱いに依存する点に注意が必要です。台湾側の課税関係としては、支店はあくまで台湾国内で発生した所得について申告・納税義務を負うにとどまり、台湾税法上、日本本社との損益通算制度が存在するわけではありません。したがって、税務上のメリットを正確に評価するためには、台湾側と日本側の双方の税制を前提としたシミュレーションが不可欠となります。
支店の設立には、台湾における「代表者(分公司経理人)」を任命する必要があります。この代表者は台湾に住所を有している必要があり、日本からの駐在員が務めるのが一般的ですが、現地での活動を円滑に進めるためには適切な権限付与とガバナンス体制の構築が不可欠です。
台湾駐在員事務所(代表人辦事處)の活用と刑事罰のリスク

駐在員事務所は、台湾において「営業活動を行わない」ことを前提とした拠点です。駐在員事務所(代表人辦事處)は、台湾会社法上、独立した法人格を持たない拠点であり、外国会社が台湾において代表者を置く場合の届出義務等を定めた会社法第386条に基づく制度運用として設けられています。
同条は、いわゆる「駐在員事務所の設置要件」そのものを直接定めた規定ではありませんが、外国会社が台湾で代表者を通じて活動する場合の法的枠組みを示す条文であり、実務上は本条に基づく登記・届出を経て、営業行為を行わない補助的拠点として駐在員事務所が運用されています。
認められる活動範囲と「業務上の法律行為」
駐在員事務所は「営業」はできませんが、会社法第386条第1項により、台湾において「業務上の法律行為」を行うための代表者を置くことが認められています。経済部の解釈(経済部92年10月29日経商字第09202221350号函)によれば、この「業務上の法律行為」には、契約の締結、入札、見積りの提示、調達(購買)、議価(価格交渉)などが含まれます。
これに基づき、駐在員事務所は事務所の賃貸借契約、備品の購入、スタッフの雇用などの事務的な法律行為を行うことができます。また、日本本社が直接台湾の顧客と契約を交わす際の前段階としての交渉や、納品された商品の検品、日本への輸出連絡業務などは、原則として駐在員事務所の活動範囲内とみなされます。
会社法第371条違反と「営業行為」の境界線
最も警戒すべきは、駐在員事務所が実態として台湾国内で「営業」を行っているとみなされるケースです。台湾会社法第371条第1項は、「外国会社は、分公司(支店)の登記を行わずに、中華民国境内において業務を運営してはならない」と定めています。これに違反した場合、行為者には「1年以下の懲役、拘留、または15万台湾ドル以下の罰金」という刑事罰が科される可能性があります。
駐在員事務所の活動が「営業行為」に該当するか否かについては、個別具体的な事実関係に基づいて判断されており、台湾の裁判例においても、補助的活動の範囲を超えた場合には刑事責任が肯定された事例が存在します。
例えば、外国会社が駐在員事務所を通じて台湾企業との間で契約を締結し、継続的に対価を受領していた事案について、裁判所が実質的な営業行為に該当すると判断したケースがあります。一方で、単なる調達業務や連絡業務にとどまる場合には、営業行為には当たらないと判断された例も見られます。
これらの裁判例が示す実務上の示唆は、形式的な名義ではなく、「誰が契約主体となっているか」「台湾国内で収益を発生させているか」「活動が反復継続しているか」といった実質に基づいて判断される点にあります。あくまで日本本社の事務連絡や補助的業務に徹することが、駐在員事務所を維持するための鉄則と言えます。
台湾の税制と進出形態別のメリット・デメリット
台湾でのビジネスにおいて、税務コストの管理は収益性に直結します。台湾の主要な税制と、進出形態による取扱いの違いを詳しく見ていきます。
営利事業所得税(法人税)と所得税法第25条の特例
台湾の法人税にあたる営利事業所得税は、一律20パーセントです。現地法人は全世界所得に対して課税されるのに対し、支店は台湾国内で発生した所得(源泉所得)のみが課税対象となります。この点は、グローバルに展開する企業にとって、二重課税のリスクや外国税額控除の適用範囲を検討する上で重要なポイントとなります。
特にIT、エンジニアリング、コンサルティング等の「技術サービス」を日本から提供する企業にとって注目すべきは、台湾所得税法第25条第1項の規定です。これは、台湾国外に本店を有する外国企業が、台湾において一定の事業活動を行う場合に、実際の原価計算が困難であることを前提として、財政部の承認を得た上で「みなし所得率」による課税を認める特例規定です。台湾国外に本社を持つ企業が、台湾国内でのコスト算出が困難な特定の事業に従事する場合、売上高の15パーセント(国際運輸は10パーセント)を所得(利益)とみなし、これに20パーセントの税率をかけることで、実質的な税負担を「売上高の3パーセント」に抑えることができる制度です。
所得額 = 収入 × 15%(みなし所得率) 所得税額 = 所得額 × 20%(法人税率) = 収入 × 3%
本特例の対象となるのは、建設請負、技術サービス、機械設備のリース、国際運輸等の限定された業務に限られており、全ての役務提供や取引形態に自動的に適用されるものではありません。また、適用にあたっては事前申請と当局の承認が必要であり、契約内容や業務実態によっては適用が否定されることもあります。
そのため、特にソフトウェア関連取引やクラウドサービスにおいては、当該取引が「技術サービス」に該当するか、それとも単なるロイヤルティ収入と評価されるかについて、契約書の設計段階から慎重な検討が不可欠です。
統一発票(GUI)制度と付加価値型営業税
台湾独自のインボイス制度である「統一発票(Uniform Invoice)」は、全ての企業が習熟すべき実務の根幹です。台湾の営業税(VAT)は原則5パーセントですが、企業間の取引、消費者への販売を問わず、政府が管理するシリアル番号付きの「統一発票」を発行することが義務付けられています。
この統一発票には、発行者と受領者双方の「統一番号(Unified Business Number, UBN)」が記載されます。税務当局はこの番号を通じて、仕入税額控除の妥当性を瞬時に把握できるため、脱税が極めて困難な仕組みとなっています。日本企業が現地で経費を精算する際、適切な統一番号が入った統一発票がなければ、原則として損金算入も営業税の控除も認められません。日常的な事務手続きにおいて、このインボイスの管理を徹底することは、台湾法人の経理業務において最も重要なミッションの一つです。
未分配利益に対する加徴課税
日本法にはない特徴的な税制として「未分配利益に対する加徴課税」が挙げられます。現地法人がその年度に得た利益を配当として分配せず、内部留保とした場合、翌年度にその未分配額に対して5パーセントの追加税が課されます。これは企業の資金流動性を高め、投資を促進するための政策的措置ですが、日本本社への送金を遅らせて現地で資金を蓄積したい企業にとっては、実質的な増税要因となります。支店はこの加徴課税の対象外であるため、利益を現地に留めて運用したい場合には、支店形態が有利に働くことがあります。
IT・テクノロジー企業に特有の許認可と規制環境

モノリス法律事務所が注力するIT分野において、台湾は「アジアのシリコンバレー」を目指す積極的な誘致政策をとっていますが、同時に通信・セキュリティ・製品安全に関する厳格な規制も存在します。
NCC(国家通訊伝播委員会)認証と通信事業
無線通信技術を用いた製品、例えばWiFi、Bluetooth、あるいは4G/5G通信を搭載したIoT機器を台湾で販売・運用する場合、国家通訊伝播委員会(NCC)による型式認証が必須です。これは公衆網への接続の安全性や、電波干渉の防止を目的としており、認証を取得せずに製品を輸入・販売すると、多額の罰金や製品の没収といった厳しい処分を受けることになります。
また、通信サービスそのものを提供する場合は、旧「第1類・第2類電気通信事業」の区分を継承しつつ整理された、現行の電気通信管理法に基づく登録や許可が必要となります。特にデータセンターの運営やクラウドサービスにおいては、情報セキュリティの観点から、データの格納場所や、特定の国(主に中国)由来の設備使用に対する制限が年々厳格化しており、最新の当局ガイドラインへの準拠が求められます。
BSMI(標準検験局)認証と製品安全
PC、タブレット、周辺機器、家電製品などの電気製品を台湾に輸入し販売する際には、経済部標準検験局(BSMI)による認証が必要です。これには、安全性テスト、電磁両立性(EMC)テスト、さらには特定の有害物質の含有制限(RoHS)への適合が含まれます。BSMI認証には、工場の検査を伴う型式認証(RPC)や、適合宣言(DoC)などの複数のタイプがあり、製品のリスクレベルに応じて適切な手続きを選択しなければなりません。
これらの認証手続きは、会社設立と並行して進める必要があります。特に認証取得には試験機関でのテストが必要となるため、製品の発売スケジュールから逆算した準備が重要です。支店や現地法人が、これらの認証の「申請人」としての地位を担うことになります。
設立手続きの実務ステップと外国人投資審査の注意点
台湾での拠点設立は、経済部を中心とした複数の官庁に対する申請の連鎖であり、日本での書類準備がその成否を分けます。
FIA(外国人投資許可)のプロセスと資本金
現地法人を設立する際、最初かつ最大の関門が「FIA(Foreign Investment Approval)」です。経済部投資審査司は、投資主体の実在性、資金の透明性、および投資制限業種(ネガティブリスト)への不抵触を審査します。
日本企業の登記簿謄本、代表者のパスポートコピー、委任状などは、全て公証役場での公証、法務省、外務省の証明を経て、最終的に日本の「台北駐日経済文化代表処」による認証(認証作業)を受ける必要があります。この一連の公証・認証作業だけで、通常2週間から1ヶ月程度の時間を要します。
資本金については、原則として最低額の制限はありませんが、事業内容を遂行するのに十分な額であるか、あるいは外国人スタッフの就労ビザ(ARC)を取得するための最低資本要件(通常500万台湾ドル以上が望ましいとされる)をクリアしているかという実務的な基準を考慮する必要があります。
銀行口座の開設と資金検証
台湾ではマネーロンダリング対策(AML)が極めて厳格に運用されており、会社設立前の「準備口座」の開設には、代表者が台湾の銀行窓口に直接出向くことが求められるケースがほとんどです。この口座に日本から外貨で資本金を送金し、台湾の公認会計士(CPA)による「資金検証(験資)」を受けることで、初めて会社登記の申請が可能となります。
就労ビザ(ARC)と労働基準法への適合
拠点を設立した後、日本からの駐在員が適法に滞在・就労するためには、労働部(労働省)から労働許可を取得し、内政部移民署から居留証(ARC)を発行してもらう必要があります。
台湾の労働基準法(労働基層法)は、日本の労働基準法と比較しても労働者保護の傾向が強く、残業代の計算、休暇の付与、退職金の積み立てなど、厳格なコンプライアンスが求められます。特にIT業界では裁量労働的な働き方が好まれますが、台湾の法令に適合した就業規則を整備しておかないと、退職時のトラブルや当局の立ち入り調査による罰則のリスクが高まります。
台湾進出後の法的責任と倒産・清算の諸問題

ビジネスは常に成功するとは限りません。撤退時、あるいは現地拠点の負債問題が生じた際の法的責任についても、進出時に理解しておく必要があります。
支店の場合、前述の通り、台湾での債務不足は直接日本本社の法的責任となります。台湾の最高法院は、外国会社が台湾支店の登記を廃止した後でも、台湾国内で行った営業によって生じた債務については、引き続き責任を負うべきであるという立場をとっています(最高法院の最新の見解に基づく)。
現地法人の場合、原則として有限責任ですが、親会社が過度に支配し、独立した法人格を形骸化させているとみなされる場合(法人格否認の法理)や、親会社が不当に資産を引き揚げた場合などは、例外的に責任を問われる可能性があります。また、会社法第381条に基づき、清算人は台湾国内の債務を完済する前に、資産を国外に移転してはならないとされており、これに違反すると清算人が個人的に損害賠償責任を負うリスクがあります。
クロスボーダー破産の場面でも、台湾は「属地主義」の立場をとる傾向があります。つまり、日本本社が日本で破産宣告を受けたとしても、その効力は当然には台湾国内の資産(支店の什器、預金、模具等)には及ばず、台湾国内の債権者は引き続きこれらの資産を差し押さえて回収を図ることが可能です。このように、台湾独自の法的規律を理解することは、進出のみならず「出口戦略」においても不可欠です。
まとめ
台湾進出における進出形態の選定は、単なる行政手続きの選択ではなく、日本本社のリスク管理体制と、台湾市場における収益モデルを法的に定義するプロセスです。現地法人、支店、駐在員事務所。これら3つの形態は、それぞれ異なる法的責任の範囲、税務上の特権、そして活動上の制約を持っています。独立した法人格によるリスク遮断を優先するのか、支店による送金課税の回避を狙うのか、あるいは駐在員事務所による市場調査から慎重にスタートするのか。いずれの選択においても、台湾会社法、外国人投資条例、および所得税法の深い理解が不可欠です。
特に、変化の激しいIT・テクノロジー分野での進出においては、製品のNCC認証やBSMI認証、さらには知的財産権の保護や情報セキュリティ規制など、会社設立と密接に関連する周辺法規への対応が事業の成否を分けます。また、台湾特有の統一発票制度や所得税法第25条の活用は、企業のキャッシュフローを劇的に改善する可能性を秘めています。
モノリス法律事務所は、IT分野の深い専門知識と、台湾の弁護士資格を保有するプロフェッショナルによる現地法令への完全な対応力を兼ね備えています。当事務所は、台湾の有力な法律事務所である椽智商務科技法律事務所(WiseBeamLaw)と強力なパートナーシップを構築しており、日本にいながらにして、台湾現地での法人登記、投資許可申請、ビザ取得、さらには複雑な許認可対応や法廷紛争の解決まで、ワンストップでのサポートが可能です。
台湾ビジネスの成功は、適切なリーガルアドバイスから始まります。当事務所と椽智商務科技法律事務所は、日本企業の皆様が台湾という有望な市場で、法的リスクを最小化し、ビジネスチャンスを最大化できるよう、全力で伴走いたします。進出形態の検討段階から、ぜひ我々にご相談ください。
Contact お問い合わせ
日本語でのご相談が可能です。
台湾進出前のご相談から、進出後の法務対応まで幅広く対応しています。






